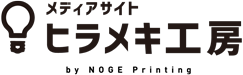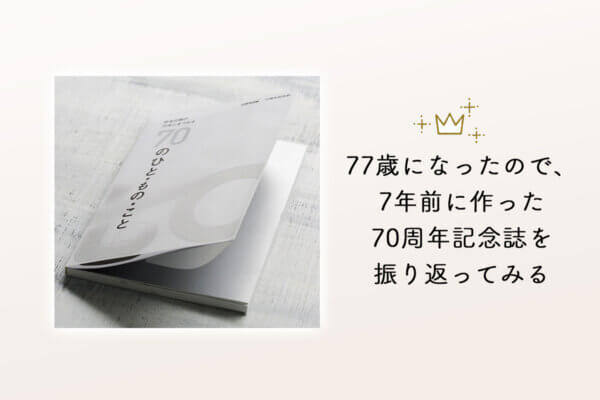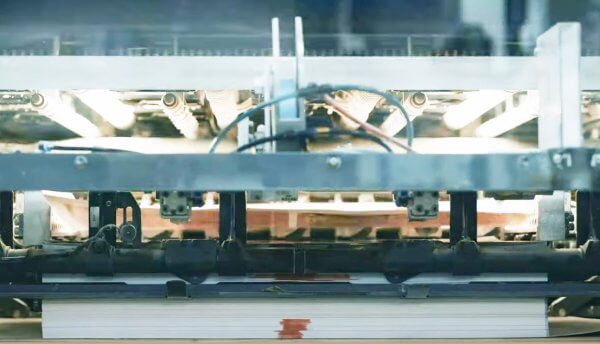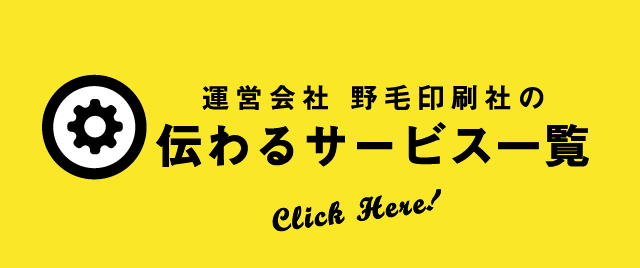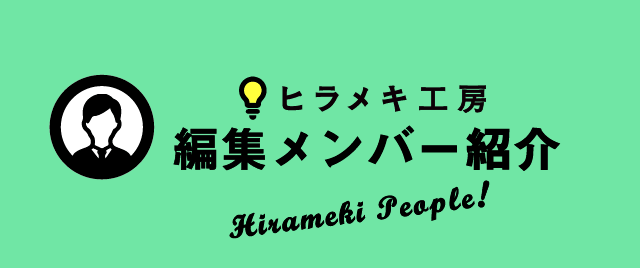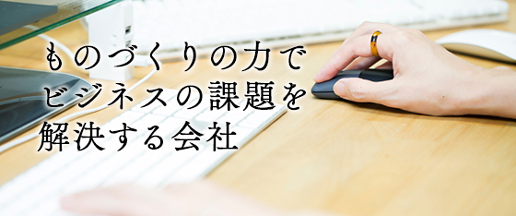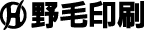昭和の印刷方法のひとつ、「謄写印刷」について
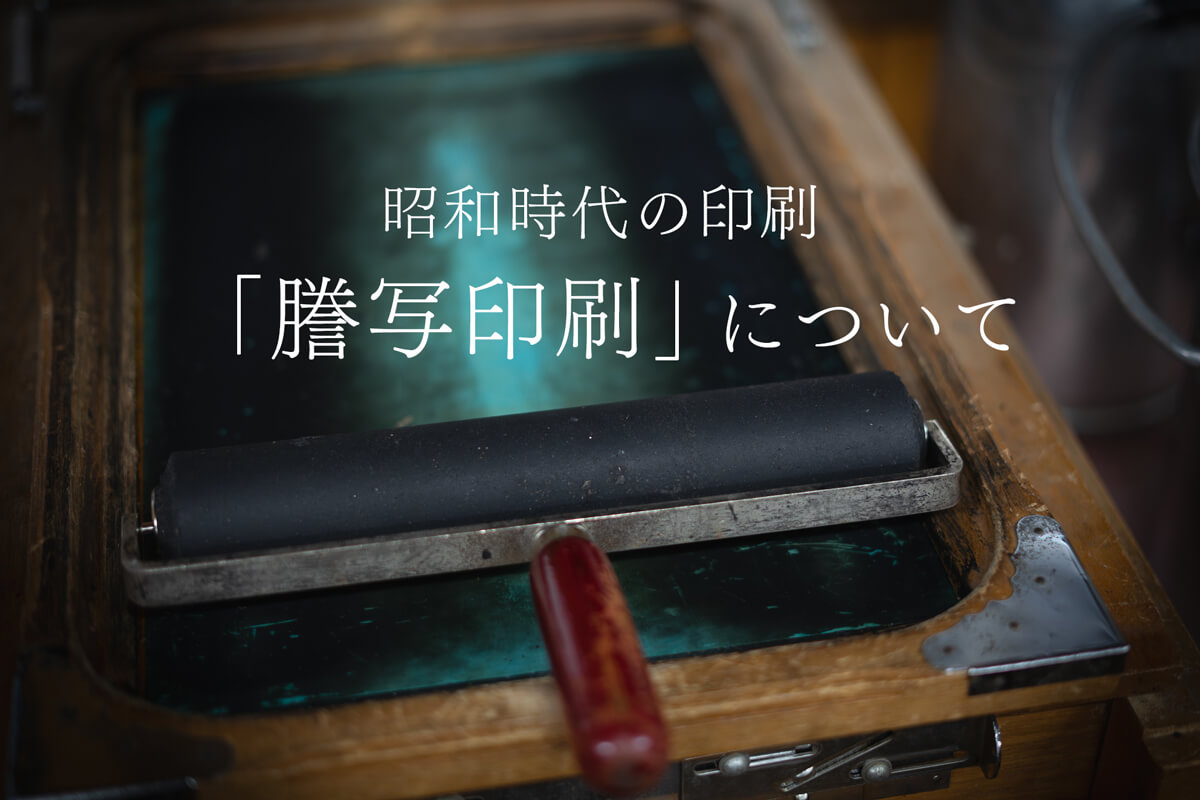
「昭和の日」にちなんで、昭和時代の印刷について書いてみようと思います。
改めて「昭和の印刷」を振り返るとなるとかなりの長編になりそうなので、今回は超スピードで昭和を駆け抜けてみようと思います。
日本の印刷の歴史をたどると、幕末にまで遡ります。印刷業のトップランナーは「活版印刷」ですが、今回は当社の成り立ちであり、活版印刷を追う立場だった「謄写印刷(とうしゃいんさつ)」に焦点を当ててご紹介します。
謄写印刷とは?
謄写印刷とは、謄写版原紙で作った版を用いる孔版印刷で、俗に「ガリ版」とも呼ばれています。ロウ引きをした原紙をヤスリの上に置き、鉄筆で文字を刻む「ガリガリ」という音から「ガリ版」と呼ばれました。
原型はトーマス・エジソンが開発した「ミメオグラフ(Mimeograph)」で、これを日本向けに改良し、1894(明治27)年に堀井新治郎父子によって謄写版が発明されました。
謄写印刷は、明治末期に筆耕派遣業として始まったと言われています。日清戦争や日露戦争で需要を伸ばし、その後は官庁や新聞社、通信社、学校などで採用され、1899(明治32)年には海外への輸出も始まりました。
1910(明治43)年頃、東大赤門前にて石田嘉一が謄写印刷店「文信社」を創業。大正時代になると謄写印刷による同人誌発行が盛んになり、制作をサポートする用例集などが作られ、多色刷りの研究も進みました。文信社からは多くの業界人が育ち、詩人で童話作家の宮沢賢治も、この仕事に携わっていたことで知られています。

昭和の謄写印刷
昭和に入ると、官庁や学校の近くを中心に、謄写印刷の店舗が大都市に増えていきました。接客カウンターを設けたその様子は、現在のコピー屋さんに近い雰囲気だったと想像されます。
謄写印刷業界が大きく動き始めたのは戦後のこと。1950年前後には謄写印刷業が全国に行き渡り、全国的な組織が結成されていきました。和文タイプライターの導入もこの頃です。機械化の波とともに、謄写印刷はタイプ印刷や軽印刷へと進化し、同時に多くの印刷会社がオフセット印刷技術の習得に取り組みました。
〈関連記事〉
謄写印刷からオフセット印刷へ

1948(昭和23)年、当時闇市で賑わっていた野毛町で創業した当社も、間口一間の店舗からスタートしました。当時神田にあった昭和謄写堂(現株式会社ショーワ)から技術を習得したり、道具・材料を調達したりして謄写印刷業に励みました。
その後は、他の謄写印刷会社と同様、家内的な手工業から機械による近代的生産へと移行。ガリ版から和文タイプへ、さらにはタイプと併用して写真植字機も導入し、オフセット印刷機の多様化・高速化・大型化を進めました。
さらに、電子製版機の実用化などを経て、印刷は高品質を求められる時代へと突入し、製造業から情報産業へと進化していきます。

昭和後期にはOA化の進展や機械のデジタル化が進み、1980年代半ばにワープロ、電子写植、電子組版機へと移行。謄写印刷は約100年にわたり日本で使われましたが、1980年代以降は徐々にタイプ印刷に移行し、姿を消していきました。
振り返ってみると、「昭和の印刷」がどれほど大きく変化していったかがよくわかります。今回はかなり駆け足でのご紹介となりましたが、実際はもっといろいろな技術、機械がありました。また改めて、より詳しい歴史をお伝えできればと思います。
〈この記事を読んだ方にオススメ!〉