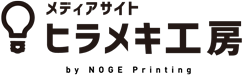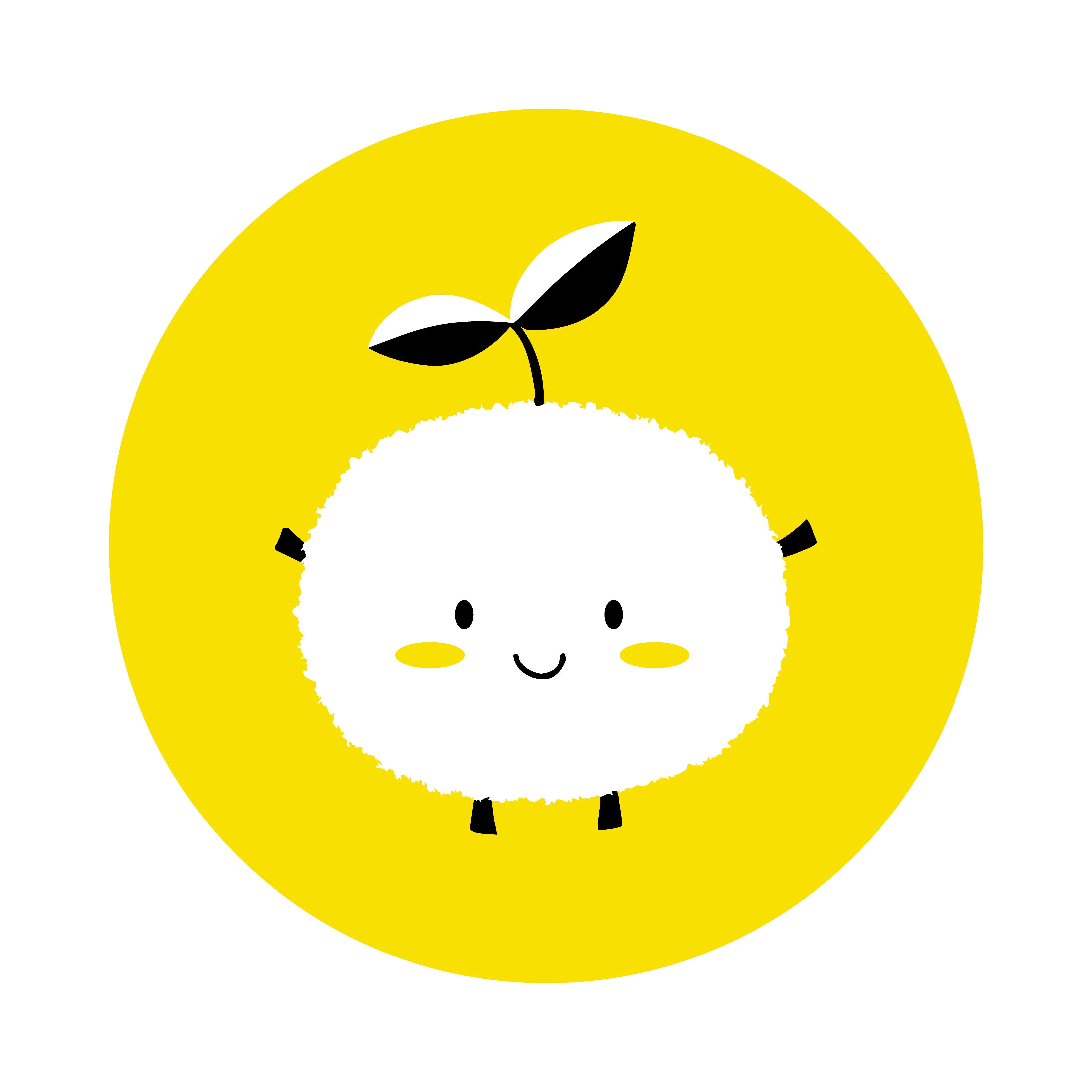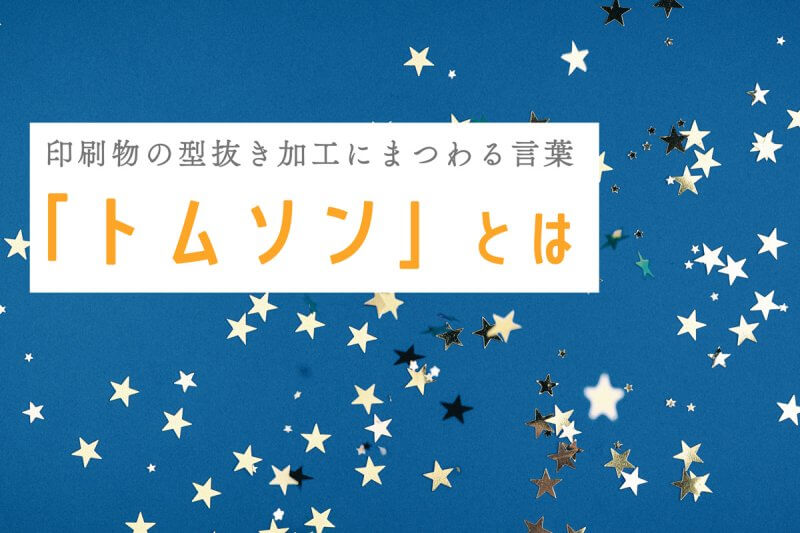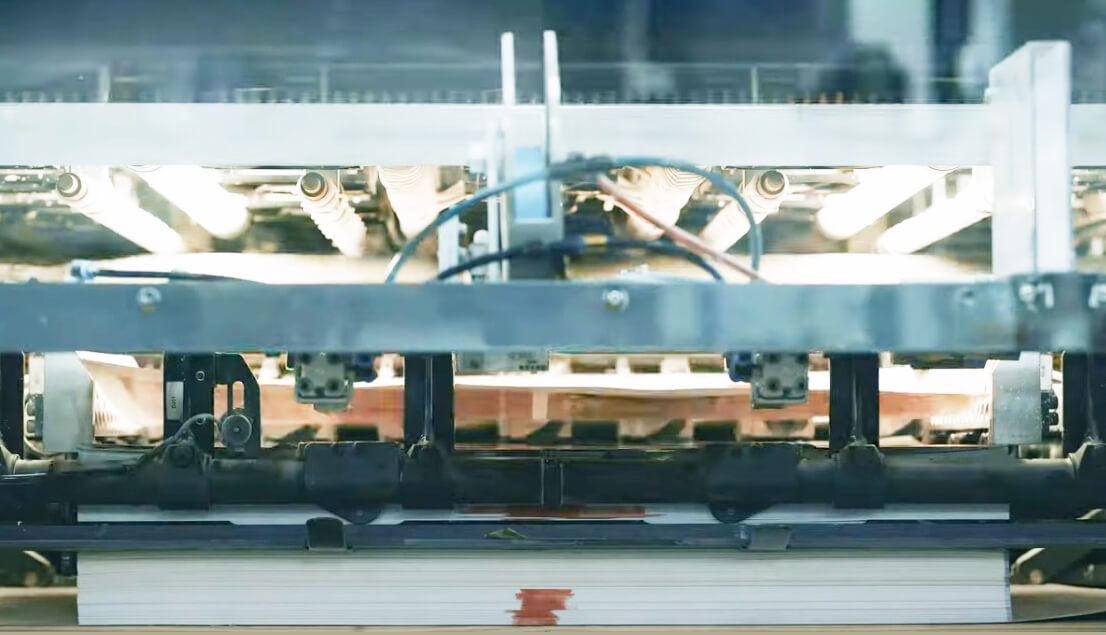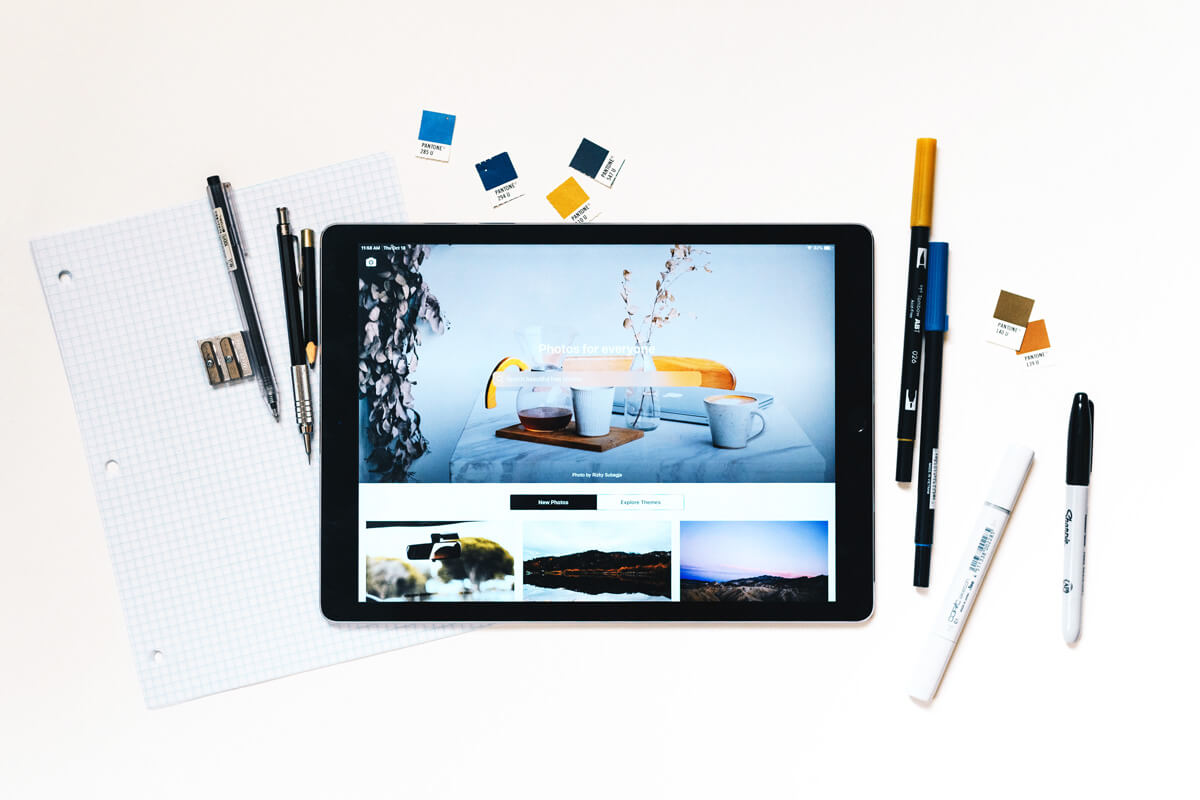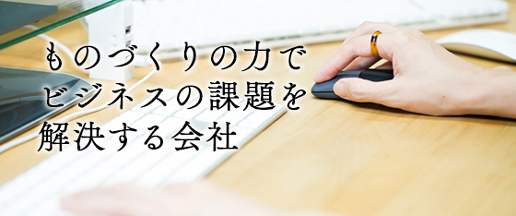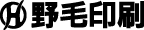今では誰もが日常的に扱う写真の「データ」。
カメラで写真を撮ると、必ずデータとして保存されます。
一番メジャーなのが、jpg(ジェイペグ)という形式です。
スマートフォン等で撮影されたデータは、ほとんどが自動的にジェイペグになります。
当社は印刷会社なので毎日何かしらの印刷物のデータを作っていますが、ジェイペグをはじめ、さまざまな形式のデータを取り扱っています。
その中で、お客さまから入稿されたデータが印刷物に適していない、という場面も。
そこで今回は、各データの特徴を解説します。
ぜひ、印刷会社・制作会社にデータを入稿する際の参考にしてみてください。
記事の後半では、印刷物のデータでよく扱う、ベクターデータとラスターデータの違いについても解説します。
データ形式の違い
意識をしていないと気づきにくいかもしれませんが、画像のデータには、形式を表す「拡張子」というものがあります。
拡張子を確認するには、
windows10では、フォルダを開き、「表示」タブ→「ファイル名拡張子」にチェックを入れる
MacOSでは、「Finder」→環境設定→「Finder環境設定」の詳細をクリック→「すべてのファイル名拡張子を表示」にチェックを入れる
で表示されるようになります。
ファイル名の最後に「.xxx」(ドット何何)とついているので、そちらを見ることでわかります。
いろいろな形式がありますので、簡単に画像の拡張子の特徴を見てみましょう。
Gif…画像データを圧縮して記録するファイル形式の一つ。256色までの画像を無劣化(lossless)で圧縮することができ、図やイラストなどの画像に向いている。
PNG…特許使用の解釈に不安のあったGIFに替わるライセンス・フリーの画像形式として開発された。PNGの特徴は、フルカラーにも8bitカラーにもすることができ、複数の透過色を指定することができる。
Tiff…さまざまな符号化方式に対応した、ビットマップ形式の画像データを保存するためのファイル形式の一つ。
ここで余談ですが、Tiff形式の画像は、圧縮による劣化が少ないという利点がありますが、データの記述(すべてデータは文字でできていますが)をカスタマイズしやすく、アプリケーションソフト独自の形式が点在しているデータでもあります。
よく目にするのは、スキャナーで読み込んだTiff形式です。
メーカーの機種によっては、制作用アプリケーションで読み込みすらできないことがありますので、入稿時には読み込めるかテストをした方が良いでしょう。
ちなみに、最初に述べたjpgの特徴を挙げると、
jpg…静止画像データの圧縮形式の一つ。 フルカラーの画像を多少の劣化を伴いながら高い圧縮率で圧縮できるのが特徴で、写真など自然画像の記録に向いている。
ということです。
長々と用語の説明が続きましたが、ポイントとしては、「圧縮」がキーワードになります。
データなので、データの容量(大きさ)によって、「圧縮」という技術に違いがあるんですね。
容量を気にするならjpgですが、圧縮されているので劣化が起きます。
大きいサイズで使う際には、ピクセル(画像の点)が粗く見えることがあります。
そのため、携帯で撮った画像を使う際には、使う大きさに注意する必要があります。
図やイラストなどの「図形」を扱うには、無劣化のGif形式かPNG形式が向いているといえるでしょう。
色の表現や透過(透明)により対応しているのはPNGなので、
単色のロゴや図、イラスト→GIF
色表現と透明を扱うロゴや図、イラスト→PNG
という基準で考えれば、かなりシンプルに問題なく扱えるかと思います。
ただ、よくあるのは、白地の角版ロゴマークがあった時に、背景を透明に使いたいという場合です。
無難なのは透明を扱えるPNGということになるでしょう。
そして、データ容量が問題になるのは、webページを作るときです。
重いデータを貼っていると表示に時間がかかってしまい、見る側にストレスを与えてしまうからです。
データの容量を適切にコントロールするなら、
自然なイメージ写真→jpg
ロゴやボタンなど→PNGやGIF
といった使い分けをすると良いと思います。
さて、印刷物になると少し事情が変わってきます。
具体的には、ポスターなどの大判の印刷物を作るときは、画像では限界があります。
拡大すると「ドット(画像の点)」も拡大され、粗さが目立ってきます。
印刷物にプリントされるサイズはとても重要になると言えますが、では大きくロゴや図を扱いたい時はどうすれば良いのでしょうか?
ベクターデータとラスターデータの違いとは
「画像」データは、すべて「ドット(画像の点)」でできています。
これをラスターデータといいます。
対して、「線」でできているのが、ベクターデータと呼ばれる形式です。
線でできているので、拡大縮小をしても粗さが一切目立たないという特長があります。
AdobeのIllustratorで作った図形は、すべてベクターデータになります。
保存形式は、「eps(イーピーエス)」と「ai(エーアイ)」。
これに対して、AdobeのPhotoshopで作られたデータは、すべてラスターデータになります。
先ほどの問いである、ロゴや画像を印刷物の大きさを気にせずに扱う場合は、ベクターデータがもっとも適しているといえるでしょう。
汎用性が格段に向上します。
その点から見ると、文字の識別や鮮明さが求められる図形やイラスト、ロゴなどには、ベクターデータが最も適しているといえます。
ラスターデータ…イメージ写真やwebなどに。
ベクターデータ…印刷物の図形やイラスト、ロゴなどに。
と考えておけば、トラブルも少なくなりそうです。
ここで一旦、ラスターデータ=画像と、ベクターデータ=図形のメリットとデメリットをまとめてみました。
ラスターデータ
☆メリット
・webで扱う際、圧縮技術により軽くでき、見る側にストレスなく表示できる。
・コンピューターで閲覧する際に、ほぼ表示ができる。
★デメリット
・元のサイズより大きいサイズで印刷すると粗さが目立ってしまう。
ベクターデータ
☆メリット
・大きさに関係なく印刷物に使える。
★デメリット
・ラスターデータしかない場合は、一から作る必要がある。
・閲覧も含め、専用のアプリケーションソフトが必要になる。
ベクターデータとラスターデータ、入稿時の注意点まとめ
実際、印刷物を作ってみてこんな経験はありませんか?
・画面では平気だったのに、印刷したらロゴが粗くなってしまった。
・webでは鮮明だったのに、印刷では写真が粗くなってしまった。
どちらもラスターデータが原因です。
では、印刷会社・制作会社に入稿する際、どんなデータを支給すれば良いのでしょうか?
大切なのは、制作物の最終的な仕上がりをイメージすることです。
作る対象とデータの形式をまとめてみました。
【Webページ】→画像データ(ラスターデータ)
・イメージや自然な写真→jpg
・図形やロゴ→GIF/PNG
【印刷物】→画像データ(ラスターデータ)と図形データ(ベクターデータ)
・イメージや自然な写真→jpg
・図形やロゴ、イラスト→epsやai
・1、2cmほどで小さく入れる図形やロゴ、イラスト→PNGも可
こちらが最適なデータ形式と言えそうです。
特にロゴや図、イラストは、鮮明さがないとイメージが大きく変わります。
データの形式を理解することで、制作物の仕上がり満足度も向上するので、ぜひ意識してみてください。
ですが、もし入稿データを作る際に「データの形式がよく分からない」といった場合でも大丈夫。
不明点があれば、入稿前に遠慮なくご相談ください。
随時適切なアドバスをさせていただきます。(※当社で制作・印刷する案件にかぎらせていただきます)
以上、画像データの形式と特徴、ベクターデータとラスターデタの違いについてでした!
〈この記事を読んだ方にオススメ!〉
▼WEB画像の最適な種類と解像度って?PNG、JPEG…どれがいい?【WEB制作時のポイント】
▼パワーポイントのおすすめフォントは?パワポが見やすくなるコツをデザイナーが解説!