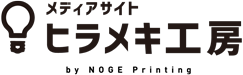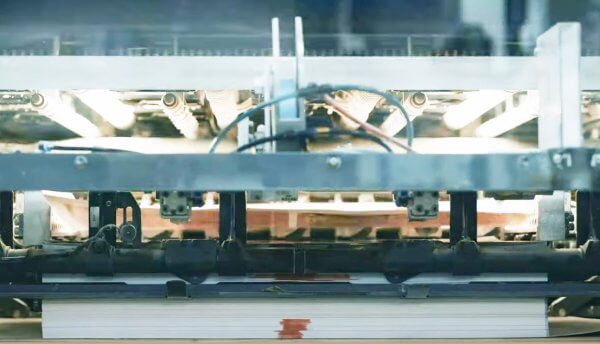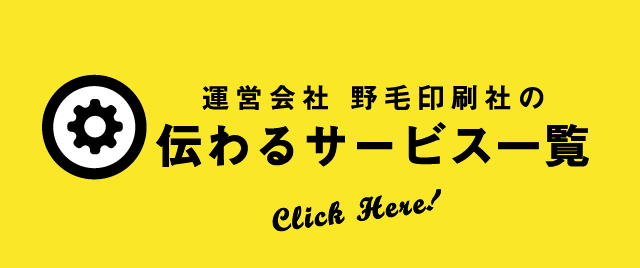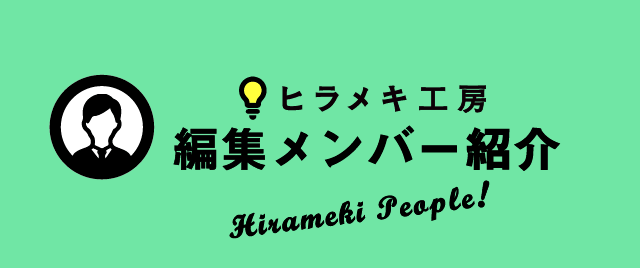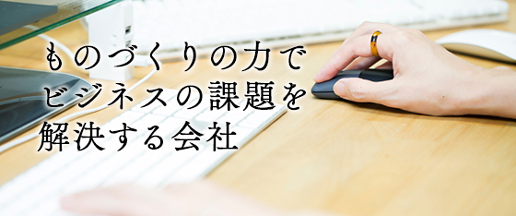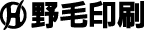9月は「印刷の月」!日本の印刷の歴史を振り返ってみた

9月は「印刷の月」
9月は、一般社団法人日本印刷産業連合会が定める「印刷の月」です。
会員団体や企業と連携し、印刷産業への認識を深め、理解の促進を図ることを目的に毎年さまざまな周知・PR活動が行われています。
では、なぜ9月が「印刷の月」なのでしょうか。
その理由は、日本で最初に活版事業を手がけ、「印刷の父」と称された本木昌造の命日が1875年9月3日であることに由来します。
今回は「印刷の月」にちなみ、日本の印刷業の歩みを振り返ってみたいと思います。
日本における印刷の歴史
日本最古の印刷物であり、現存する世界最古の印刷物とされるのが「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」です。
これは奈良時代の770年、法隆寺をはじめとする10の国分寺に、10万基ずつ小塔を奉納し、その中に納められた印刷物です。
版が木製であったのか金属製であったのかは不明ですが、当時すでに印刷に携わる業者が存在していたと考えられます。
その後約300年間は「源氏物語」をはじめとする多くの書物がつくられましたが、いずれも手書きによるもので、印刷は用いられませんでした。
木版印刷として登場するのは、平安末期の「成唯識論(じょうゆいしきろん)」だといわれています。
以降、鎌倉・室町時代には、寺院を中心にさまざまな経典が印刷・出版されました。
この頃までは、読み書きのできる一部の武士や僧侶のための印刷でしたが、江戸時代に入ると読み書きのできる町民が増えました。3代目将軍・家光の時代には木版印刷による書物の出版が盛んになり、浮世絵などが普及し庶民の間にも浸透していきました。
ヨーロッパの印刷発展の歴史
一方ヨーロッパでは、1450年にグーテンベルグが活版印刷術を発明。
活版印刷機やプレス印刷機を用いた印刷が盛んになり、世界中に広まっていきました。
日本では江戸末期、オランダ語の翻訳を業としていた本木昌造が、1848(嘉永元)年にオランダの貿易商から活字と印刷機を購入。自ら鉛活字をつくり、自著『蘭和通弁(らんわつうべん)』を印刷しました。
1870(明治3)年には「新町活版所」を創業し、日本初の民間活版事業を開始。その後活版印刷は、新聞や雑誌、書籍の分野で急激に浸透していきました。
1876(明治9)年には、勝海舟が命名したとされる「秀英舎」(現・DNP)が創業し、日本初の本格的な印刷企業が誕生しました。
さらに1914(大正3)年にはオフセット印刷が日本に伝わり、その後もグラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷など多様な印刷技術が登場。
謄写版の発明や筆耕派遣業から生まれた謄写印刷なども加わり、印刷産業を支えていきました。

日本の印刷産業の変化と今
印刷産業はオフセット印刷を中心に成長し続けましたが、1991(平成3)年以降は縮小に向かいます。
その大きな要因の一つが、デジタル化による印刷製造プロセスの革新です。
それまで手作業で行われていた工程が、DTPの普及により1台のPCで完結できるようになりました。
このとき積極的にデジタル化を進めた印刷会社が生き残り、立ち後れた会社との差が命運を分けたと言われています。
以降、印刷業は単に印刷物を製造する仕事から、情報を加工して発信する仕事へと移行していきました。
これからの印刷業に向けて
時代の変化とともに大きな転換を遂げてきた印刷産業。
当社の印刷サービスも、時代にあわせてさまざまな取り組みを行っています。
この「ヒラメキ工房」でも、印刷の新しい可能性を多数発信しています。
ぜひあわせてお読みください!