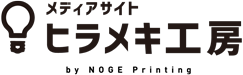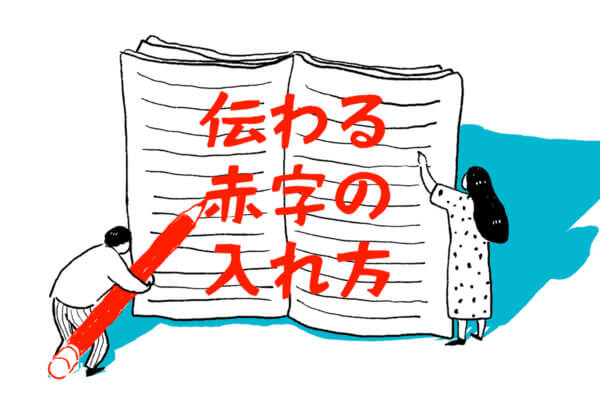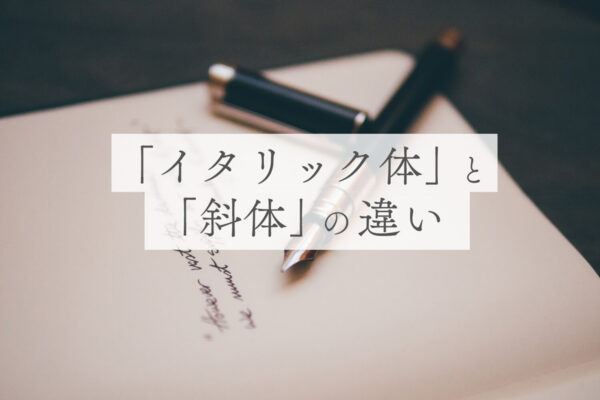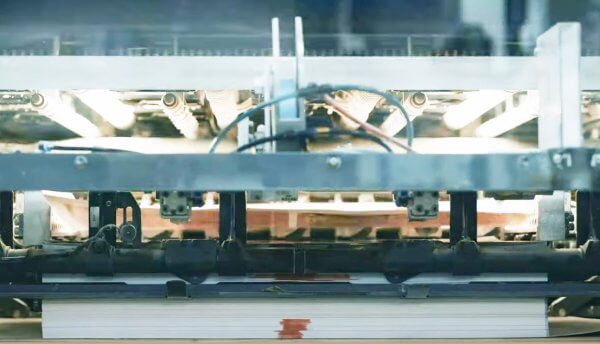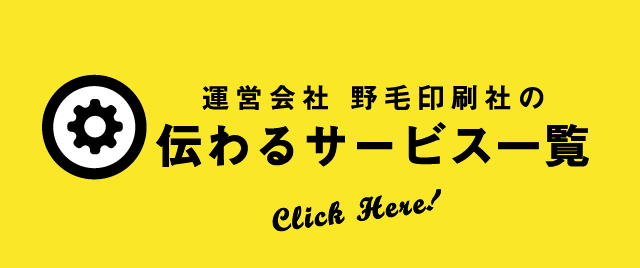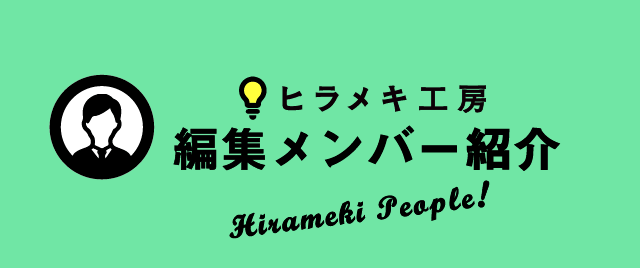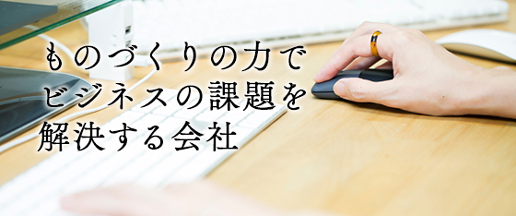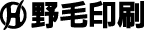ひらく?とじる?校正時の選択のポイント

皆さんは年賀状に「あけましておめでとうございます」と書くとき、どのように表記しますか?
すべてひらがなにしますか?それとも漢字を使いますか?
先日、過去の年賀状を整理していたところ、「明けましてお目出度う御座います」と印刷されたものを見つけました。最近ではこのような表記はだいぶ減った気がしますが、今でも使われることがあります。
今回は、「ひらく」か「とじる」かの選択についてお話しします。
「ひらく」「とじる」とは?
先ほどの「お目出度う」という表記ですが、「おめでとう」は「お芽出度う」と書かれることもあります。これらは、漢字本来の意味とは関係なく、音や訓を借りて当てはめた「当て字」です。日本語にはほかにも多くの当て字があります。
もちろん、漢字のほうが意味を伝えやすい場合はそのまま使いますが、筆者は基本的に意味が伝わりにくい当て字は「ひらく」ようにしています。
さて、ここで出てきた「ひらく」という言葉。
「ひらく」とは、広告・出版・印刷業界の専門用語です。広告コピーのライティング、出版・印刷物の文章作成、あるいは校正・校閲作業などで漢字をひらがなにすることを業界用語で「ひらく」といいます。
例えば、以下のような表記を見たとき、ひらがなにした方が読みやすいと感じることはありませんか?
・所謂→いわゆる
・沢山→たくさん
・大体→だいたい
・矢鱈→やたら
・兎に角→とにかく
・滅多→めった
逆に、ひらがなを漢字にすることを「とじる」といいます。
「ひらく」か「とじる」かの選択は、文章を書くすべての人にとって、また、校正者や編集者にとって悩ましい問題です。
「ひらく」と表現するようになった理由は明確には分かっていませんが、ひらがなにすることで文字数が増え、文章が開いたように見えるからかもしれません。
では、どのように「ひらく」と「とじる」を判断すればよいのでしょうか?
校正時の「ひらく」「とじる」の判断ポイント
近年、パソコンでの文字入力が一般的になり、難しい漢字も簡単に変換できるようになったため、漢字が多い文章になってしまいがちです。
しかし、新聞社などが定めているように、常用漢字であっても難読な漢字は避けるなど、読みやすさを考慮することがライターや校正者には求められます。
表記のルールに絶対的な正解はありませんが、漢字本来の意味が薄れた言葉はひらがなにする、というのが現在の主流の考え方になっているようです。
また、一般的に以下のような品詞は「ひらく」ほうがよいとされています。
・副詞(しばらく・だいぶ・おそらく など)
・形式名詞、補助名詞(こと・もの・わけ など)
・補助動詞(~しておく・~してみる など)
・連体詞(いわゆる・いろんな など)
・接続詞(また・それから・しかし など)
・副助詞(まで・ほど など)
文章全体としては、「漢字3割:ひらがな(カタカナ)7割」がバランスのよい比率とされています。
当社は印刷会社であり、文章の校正を行うこともあります。校正の際は、お客さまが定めるレギュレーションを優先しつつ、内容や読者層を考慮しながら、「ひらく」か「とじる」かを判断するよう心がけています。
〈この記事を読んだ方にオススメ!〉