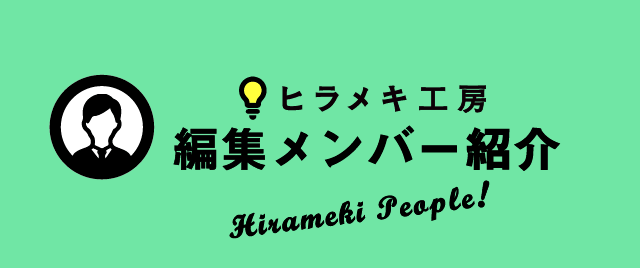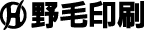【日本のマスク文化は黒マスクではじまった?!】意外なマスクの歴史

緊急事態宣言が2021年3月21日で解除されますが、新型コロナウイルスのことを気にせずに安穏な暮らしができるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。
感染予防の基本としてマスクの着用が浸透している日本ではありますが、最近ではそのマスクが公衆衛生用品の域を超えた、新しい文化になってきたような印象があります。
そこで今回は、「日本におけるマスクの文化と歴史」について調べてみました。
日本のマスク文化のはじまり
そもそもマスクの起源は、古代ローマ。鉱山などで働く人々を粉塵から守るためのものだったといわれていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチが16世紀に布製のマスクを発明したという話も存在します。
マスクの語源は「道化者(Masque)」。「正体を隠す」という意味で、防塵、防毒などに使用されていたものが、19世紀末に欧米で医療用品としての役割を果たすようになったとされています。
日本に登場したのは、明治時代初期の頃。空気をろ過して使うしくみのものが最初と言われています。
1879(明治12)年に発売された「レスピラートル(呼吸器)」という商品は、炭鉱や工場などでの粉塵除けを目的として使われていたため、汚れが目立たない「黒マスク」でした。
そんなマスクが衛生用品として広く認知されるようになったのが、大正時代、世界中で猛威を振るったスペイン風邪の流行時。
1918(大正7)年から1921(大正10)年にかけて流行したスペイン風邪は、日本で約2,400万人が感染し、約38万人が死亡したとされます。
当時国が作成したポスターには、電車内で黒いマスクをつけた乗客たちのなかに一人だけマスクなしの男の様子が描かれ「マスクをかけぬ命知らず!」のコピーが添えられていました。
ちょうどその頃、100年前の1920(大正9)年に刊行された雑誌『改造』に、マスクを手放せなかった文豪の日常が綴られています。
菊池寛の短編小説「マスク」には、スペイン風邪への感染を恐れた主人公がとった行動が描かれているのです。
医療用に白マスクの需要が大きく伸びたのはこの頃のようで、主人公は野球観戦に訪れた球場で見かけた黒マスクの青年に憎悪を感じています。「毎日の新聞に出る死亡者数の増減に一喜一憂した」などの描写は、コロナに怯える今の私たちと同じ心境であったことが窺えます。
マスクは、その後はずっと白マスクの時代が続き、布マスクからガーゼマスクへ、80年代には花粉症対策で多くの人が使うようになり、使い捨ての不織布やポリウレタンを素材としたマスクが主流となりました。
そして今、さまざまなメーカーが製造するマスクは素材も形も色も柄もいろいろ。自分だけの手づくりマスクも登場しています。マスクをファッションの一部として楽しむ時代がくることを、ちょっと前までは誰が想像したでしょうか。昔からマスク文化が定着している日本だからこそ、受け入れも早かったのかもしれませんね。
《関連記事》
こちらもあわせてお読みください。