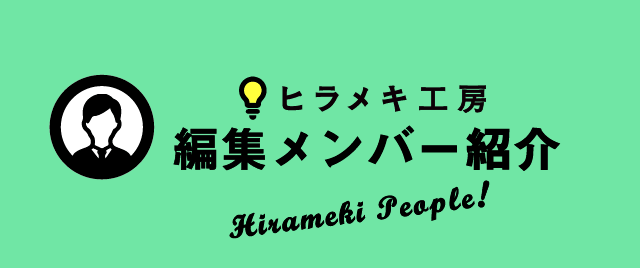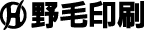古典名作の普及版として始まった「文庫本文化」。その歴史を考察

最近、この『ヒラメキ工房』でアクセス数をぐんぐん伸ばしている記事があります。
それがこちら。
皆さん、「単行本」と「文庫本」の違いについて知りたい方が多いようです。
今回は、そんな人気記事の傾向も踏まえながら、「文庫本」について深く掘り下げてみようと思います。文庫本が出版され、世の中に広まっていた「文庫本文化の歴史」を考察していきます。
古典名作の普及と文庫本文化
当社の印刷工場がある横浜の金沢区。
そこにある称名寺は、鎌倉幕府の貴重な遺産であり北条実時が建立した寺として知られています。
その隣にあるのが、実時が設けた日本最古の武家文庫「金沢文庫」です。
「文庫」は文書や図書を収蔵する書庫を意味するもので、もともと音読みの「ふみくら」と呼ばれていました。
文庫とは別に、日本には古くから宮中の書籍や経典などを保管する「図書寮」という施設が存在しています。
明治時代中期に欧米の「Library」の制度が伝わった際に、図書を保存する建物という意味で「図書館」と訳されたため、大規模な施設は「図書館」、学級文庫のように小規模なものは「文庫」という呼び名で使い分けられるようになりました。
そして、ここからが「文庫本」の話。
「文庫本」が出版のひとつの形態として日本に定着したのは、1914(大正3)年に創刊された『新潮文庫』や、1927(昭和2)年に創刊された『岩波文庫』と言われています。
ですが、実際は明治時代に発行された文庫本がありました。
それが1903(明治36)年に発行された富山房の『袖珍名著文庫』です。
明治末期から大正にかけて、同じような文庫本が多数出版されました。
筆者の書棚にも1910(明治43)年に出版された三教書院の『袖珍文庫』が存在します。

三教書院 袖珍文庫『文章軌範』(左)、『近世説美少年録』(右)
「袖珍」という呼び方は、袖に入れて持ち歩けるほど小さいという意味から使われたもの。
江戸時代にはすでに小型の書物を「袖珍本」と呼んでいたようで、「珍」には「尊い」、「貴重な」といった意味があるようです。
改めて手持ちの『袖珍文庫』を見てみると、いわゆる文庫本サイズのA6判(148㎜×105㎜)より一回り小さく、B7判に近い125㎜×90㎜。
製本はクロス装で、表紙にはイチョウの葉をあしらったデザインの型押し、背文字には金箔が施されています。
本の冒頭に記されているのは、「泰西(西欧)にはカッセル、レクラム等という書肆(書物)があって、どんな名著でも極めて簡素な小冊子にして極めて廉価に販売する」という発刊の主旨。
つまり袖珍文庫は、1886(慶応元)年に創刊されたイギリスの『カッセル国民文庫』と、1867(慶応2)年に創刊されたドイツの『レクラム文庫』を手本とする、古典名作の小型廉価普及版でした。
文庫本は昭和初期のブームの後、戦後には角川文庫、ハヤカワ文庫、講談社文庫、集英社文庫、文春文庫などが次々と創刊。何度もブームを巻き起こしました。
もちろん現在も幅広いカテゴリー、数多のレーベルの文庫本が、多くの愛読者に支持されています。
手軽に読書するならスマホやタブレットで十分という現代。
しかし、移動時間や隙間時間に小さな本の紙の手触りを感じていただき、日本のひとつの文化としての文庫本を末永く愛し続けてほしいと願っています。
《関連記事》